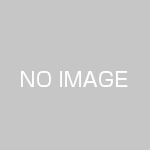『社会的フレイルを有することは、うつ傾向と関連する』ということもそうですし、身体的フレイルが社会的フレイルを引き起こすということはお店を運営する中でずっと感じていたこと。
ちづるでお過ごしいただくことに魅力、価値を感じられなくなったという方もいらっしゃると思いますが、お客様の来店頻度・状況などを分析してみると社会的フレイル・身体的フレイルが原因で去られていくお客様も一定数いらっしゃることが分かりました。
もちろん昨今の消費傾向から価値観の変化ということも大きいと考えていますが、加齢に伴う心身の衰えが原因の場合、こうした何気ない変化が社会生活機能全般の低下を招くトリガーとなってしまうのかも。
今日はそんなお話をさせていただこうと思います。
リタイアされる直前に奥様が重いうつ状態になられたことから家事全般をご主人様が担われていたようで体力的にも相当お辛いものがあったよう。
「ここに来るのが月に一度のご褒美なんだよ!」そう仰られてちづるをご利用下さっていましたが、1年ほど前からお越しになられなくなってしまいました。
リタイア後、新たに就かれたお仕事も大変なご様子でしたし、加えて家事全般をこなさなくてはいけないなど、私たちに何かできることはないか。ということから度々お惣菜などをお届けをさせていただいていましたが、お会いする度にその方自身うつ状態にあることを感じ、最後にご連絡をさせていただいた時は気力を全く感じることのないお声になってしまっていて、電話越しに深刻度がより増していることが分かるほどでした。
お酒を召し上がられなくても明るい方でしたし、リタイア後の人生設計も「良い会社に入って良かった!」と喜んでいらっしゃっただけに余りにもショックな出来事でしたが、誰にでも起きうる危うさを感じました。
組織に属する方の場合、息を抜く場(第三の居場所)を放棄することは社会的フレイルを引き起こす一因になると思うんですね。
「新たな場所を見つければ足りる話」ということも思いますが、それを見つけることができない。という方の場合、それまで居た第三の場所から離れてしまうのは危険だと思うんですね。
サードプレイスがスナック・社交飲食店である必要はありませんが、本当の自分・本当に近い自分、鎧を着ることで居心地が良ければそれも良いと思いますが、そうした場所から離れることは精神的フレイルを招きやすくしてしまうと思うのです。
奥様のメンタル不調の原因は夫源病によるもののようですが、ご主人様が現役を退かれたことにより、これまでの夫婦間における適度な距離、奥様にとって心地良さを感じていた場所を失ってしまったことが夫婦間のバランスを大きく崩してしまったのでしょう。
こちらの方の場合、夫源病ではなく離職後の”何もしない生活”が長く続いたことにより意欲低下を招いてしまったものだと思われますが、どちらの場合でも気力、体力の衰えが始まる60代後半から70代前半をどう過ごすか。に係っていると思うのです。
急激な意欲の低下はうつ状態を引き起こす大きな要因と考えていますが、元に戻ろうとすれば時間も費用もかかってしまいますものね。
戻ることができれば良いのですが、シニアの場合 健康寿命ということも考えなくてはいけませんから、現役時代に習慣化されていたことをリタイアを機にやめてしまうという判断をすることで辛い老後を招く結果に繋がってしまうこともあるようですから、ゆっくりフェードアウトさせるよう意識しておきたいところ。
お話をさせていただきました以外 色々な方がいらっしゃいます。
もちろん有意義なシニア生活を送られている方もいらっしゃいますが、私の感覚では男性の場合、時間を持て余していらっしゃる方が多いように感じていて、現役を退かれる辺りから始まる様々な喪失体験が積み重ねによる鬱や認知機能の低下を引き起こさないよう”喪失体験を埋める”工夫をすること。事前に備えておくことの重要性を感じていて、そう言った意味も含めてちょいカラサロン夜改・ちょいカラサロンを始めた訳ですが、健康と言えば身体的なことをイメージされる方が多いのでしょう。
「飲みに行くこと=娯楽=不真面目という考え方が昔から根強くあるからね。」
「夜遅く帰ると近所から噂されるから、、、」
これは多くのお客様から伺ったお話で地域的なことだと感じていますが、スナックバーちづるもちょいカラサロンもそうした環境の中にあることから連日閑古鳥が大騒ぎをしている訳ですが、怖いのは意欲が衰えてしまうことで、これは「近頃、関心が薄れた。」という小さな小さなサインから始まるようですから娯楽を怠惰、良くないものと考えるのではなく、”心豊かな生活を行う上で必要な潤滑油”と考え方を切り換えられることをお勧めさせていただきたいと思います。
身体的に不安なことがあっても何かをしたい!始めたい!という意欲・欲動を失わない限りそれに向けた努力・思考が働きますが、意欲・興味が湧かなければカラダもココロも閉じこもったままになってしまうでしょうし、それが認知・身体機能の低下の始まりになるようですし、加齢によるものと諦めてしまえば戻れるものも戻れなくなってしまうようですので見落とさないよう注意が必要。
健康を損なうことで意欲が低下するじゃないか!という方もいらっしゃると思いますが、身体の不自由な方が多く活躍されていらっしゃる事実を見ても意欲の大切さがお分かりいただけると思います。
”WHO(1946)は、「健康とは単に病気でない、虚弱でないというのみならず、身体的、精神的そして社会的に完全に良好な状態を指す」と提唱している”の通り、このお仕事(ちょいカラサロン)を運営する中で精神的なことこそ大切なのではと感じるのは著しい身体的衰えはあってもお越し下さる方とそうでない方の違いによるもの。
身体的衰えがあっても社会と関わろうとする意欲がそれをカバーし、ココロの健康を維持できることはお客様より教えていただいたことで私たちもお勉強をさせていただいていますが、こうしたことをもっと多くの方に知っていただければいいのに。と思いつつ、実店舗同様このサイト・ブログも閑古鳥、、、😅
本当に必要とされる方の目に留まることを心より祈っています。
おしまい。