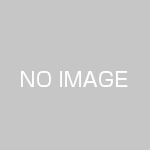岡本 響子 天理医療大学 医療学部 看護学科
オープンダイアローグって何?
ミーティングではすべての参加者に平等に発言の機会と権利が与えられる。クライエントは幻覚や妄想などの病的体験についても話すが,その体験は他の参加者によって否定されることはなく,むしろ肯定的なフィードバックを与えられる。しかしオープンダイアローグは,語る主体としてのクライエントをそのまま肯定するものでもない。参加者同士がお互いの声を聴き,それぞれが自分の気持ちや考えを発することで,お互いへの理解が深まり,新たな共通の理解に到達したりする。
オープンダイアローグの基本原則オープンダイアローグの原則としてSeikkulaは7 つの原則をあげている(表1)。
オープンダイアローグにおいても「患者patient」と「専門家professional」という区別は存在する。ただ「専門家が指示し,患者が従う」といった上下関係は存在せず,可能な限り相互性を保った状態で対話をすることが望ましいとされる。ではどうしたら対話的になるのだろうか。
Seikkulaは対話的実践とは,人間の基本的な価値に応答することであると述べている。我々は専門家としてトレーニングを受け,「介入」することにあまりにも馴染んでしまっている。介入によって問題や症状をコントロールできると信じている。しかし最も重要なことはその前にある。人は関係性の中に生まれ,関係性が私たちの存在を作る。人が集まり苦しみや痛みの感覚をいかに共有するかが重要になる(Seikkula,2018)。Seikkulaは精神病性障害の行動は「起こったことへの反応」として生じているわけで,我々が集まって行うべき介入は「何が起こっているのかを理解する」ことであると。未だ言葉にならないものに言葉を与えていくために集まるのだと語っている。